社会
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
埼玉・北本の飲食店4軒で窃盗相次ぐ

22日未明から明け方にかけて、埼玉県北本市内で、ラーメン店など飲食店4軒で現金などが盗まれる事件が相次ぎました。警察は同一犯の可能性もあるとみて関連を調べています。
22日午前3時前、埼玉県北本市のラーメン店で、閉店時間中に裏口のドアが壊されているのが見つかりました。この店に他に被害はありませんでしたが、その後、2時間の間に、近くの飲食店でも同じように閉店中にドアや窓が壊され、レジや現金が盗まれる被害が3件相次ぎました。被害額はあわせておよそ5000円でした。
被害にあった4軒の飲食店はJR高崎線の北本駅近くにあるラーメン店やうどん店で、いずれも国道17号線沿いのおよそ2キロの範囲にあります。
警察は同一犯の可能性もあるとみて、付近の防犯カメラを調べるなどして捜査を進めています。(22日13:37)PR -
語り継ぐ「ひめゆり」の記憶=元学徒ら高齢化、講話終了-沖縄戦から70年節目に

修学旅行生を前に太平洋戦争末期の沖縄戦の体験を話す、ひめゆり平和祈念資料館の島袋淑子館長=22日、沖縄県糸満市の同館
沖縄県糸満市のひめゆり平和祈念資料館で、1989年の開館当初から行われてきた元ひめゆり学徒による講話が22日、最終日を迎えた。高齢化により続けていくことが困難と判断、沖縄戦から70年の節目に引退を決めた。この日、最後の講話を終えた島袋淑子館長(87)は「戦争を知らない人たちにどう話したら分かってくれるかと、焦ったり悩んだりしている。どれだけ伝わったか心配だが、一つのけじめをつけたい」と話した。4月以降は、戦争体験のない若い世代が学徒らの記憶を伝える役割を引き継ぐ。
「包帯を外すとうじがポロポロ、うみもいっぱい。あまりの悪臭に失神しそうになりました」。今年2月、学徒隊で最高学年だった大見祥子さん(89)が壕(ごう)での看護体験を語ると、修学旅行生ら約200人が入ったホールはしんと静まり返った。
沖縄本島南部の地図を使い、爆音や兵士のうめき声を再現しながら語る声が静かに響く。撤退命令が出された朝、大見さんは重傷を負った友人を残し、壕を出た。「『誰か助けてちょうだい』と小さな声が聞こえて…」と声を詰まらせた。「戦争って本当に大変なんです」。絞り出すように、何度も繰り返した。
動員された学徒隊240人のうち、生存者は104人。開館当初27人いた証言員も、今は9人となった。講話は多いときで年間1000回以上に上ったが、2013年度は350回にまで減った。
後継者育成のため、08年には講話を引き継ぐ説明員らと戦跡を巡った。説明員の1人で同館学芸課の尾鍋拓美さん(33)は「体験者に代われるか不安はあるが、伝えたいという気持ちは同じ。学徒たちの生きざまも伝えていきたい」と話す。島袋館長は「世の中がどんなに変わっても、毅然(きぜん)として平和の尊さを伝えてほしい」と力を込めた。 -
国際協力でガンマ線天文台=日本担当の望遠鏡、9月にも建設

国際宇宙ガンマ線天文台(CTA)の大口径望遠鏡(反射鏡の直径23メートル)の想像図。日本が主に担当し、スペイン・カナリア諸島に建設される可能性がある(CTAコンソーシアム提供)
宇宙から飛来する超高エネルギーのガンマ線を観測する望遠鏡群「国際宇宙ガンマ線天文台(CTA)」の建設計画が進み、日本が主に担当する大口径望遠鏡の1基目が、今年9月からスペイン・カナリア諸島に建設され始める可能性が高まった。
紫外線よりはるかにエネルギーが高いガンマ線は、巨星が寿命を迎えて超新星爆発を起こした後の残骸や、銀河の中心にある超巨大ブラックホールの近くなどから放出されるが、発生メカニズムや詳しい性質は謎が多い。
CTAは、地球の南北2カ所に口径が大中小3パターンの望遠鏡を合計118基も設置する計画。2020年に完成すれば、謎の解明が大きく進むと期待される。 -
新幹線、待ち切れないと出迎え 北海道北斗市、あと1年

1年後の2016年春の北海道新幹線開業を盛り上げようと、新幹線の「H5系」車両を出迎えるイベントが22日、終着・始発駅になる新函館北斗駅(北海道北斗市)で開かれ、開業を待ち切れない地元の北斗市民約100人が、建設中のホームで歓迎した。
午前11時ごろ、H5系がゆっくりとホームに入ると、手に持ったライトを振り、集まった市民が出迎えた。高谷寿峰北斗市長は「あと1年で開業するのは、感慨無量の思いだ」とあいさつ。記念撮影の後、H5系は近くの車両基地に戻った。
祖父母と参加した、北斗市の小学5年荒町堅君(11)は「H5系は新しくきれいで、格好良かった」と話した。
-
語り継ぐ「ひめゆり」の記憶=元学徒ら高齢化、講話終了―沖縄戦から70年節目に
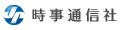
沖縄県糸満市のひめゆり平和祈念資料館で、1989年の開館当初から行われてきた元ひめゆり学徒による講話が22日、最終日を迎えた。高齢化により続けていくことが困難と判断、沖縄戦から70年の節目に引退を決めた。この日、最後の講話を終えた島袋淑子館長(87)は「戦争を知らない人たちにどう話したら分かってくれるかと、焦ったり悩んだりしている。どれだけ伝わったか心配だが、一つのけじめをつけたい」と話した。4月以降は、戦争体験のない若い世代が学徒らの記憶を伝える役割を引き継ぐ。
「包帯を外すとうじがポロポロ、うみもいっぱい。あまりの悪臭に失神しそうになりました」。今年2月、学徒隊で最高学年だった大見祥子さん(89)が壕(ごう)での看護体験を語ると、修学旅行生ら約200人が入ったホールはしんと静まり返った。
沖縄本島南部の地図を使い、爆音や兵士のうめき声を再現しながら語る声が静かに響く。撤退命令が出された朝、大見さんは重傷を負った友人を残し、壕を出た。「『誰か助けてちょうだい』と小さな声が聞こえて…」と声を詰まらせた。「戦争って本当に大変なんです」。絞り出すように、何度も繰り返した。
動員された学徒隊240人のうち、生存者は104人。開館当初27人いた証言員も、今は9人となった。講話は多いときで年間1000回以上に上ったが、2013年度は350回にまで減った。
後継者育成のため、08年には講話を引き継ぐ説明員らと戦跡を巡った。説明員の1人で同館学芸課の尾鍋拓美さん(33)は「体験者に代われるか不安はあるが、伝えたいという気持ちは同じ。学徒たちの生きざまも伝えていきたい」と話す。島袋館長は「世の中がどんなに変わっても、毅然(きぜん)として平和の尊さを伝えてほしい」と力を込めた。
