産業・経済
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
「遺伝子診断」でがんの性質にあわせて治療薬を選ぶ時代に

がんは不治の病ではない。研究の現場を訪ね歩くと、そう感じる。アプローチは1つではない。治療法はあらゆる角度から進化している。研究者たちのほとばしる熱意を感じてほしい──。
がんは、特定の遺伝子変異が積み重なることで発症する。食習慣や発がん物質への暴露などの環境因子や生命活動の中で生じる化学反応により、後天的に変異が生じるケースがほとんどだ。しかし「がん患者の1割程度は、生まれつきの遺伝子変異が大きな要因となっている可能性がある」と埼玉県立がんセンターの赤木究医師はいう。
ヒトはそれぞれの両親から遺伝子セットを受け継ぐので、同じ役割の遺伝子を2つ持っている。例えば、がん抑制遺伝子として有名な「p53遺伝子」は、2つとも正常であれば、がん化する細胞を自死(アポトーシス)へと誘導する働きがある。しかし、変異により機能が失われると自死が誘導されにくくなり、がんが生じやすくなる。
こうした変異を両親のどちらか一方から受け継いだ場合は、正常な2つを持つ人たちに比べ、若くしてがんを発症しやすい。また、体中の細胞に変異が伝わっているため、さまざまな臓器でがんを発症する可能性がある。それに加え、タバコなどの環境因子が加わることにより、変異の蓄積が加速され、発症も加速してしまう。
これまでに、特定のがんとの関係が深い原因遺伝子が多く判明している。その原因遺伝子に変異があれば、特定の臓器がんを発症しやすくなる。
そのうち最も頻度が高いものにリンチ症候群(HNPCC)がある。大腸がんや子宮体がんなどの発症リスクが高まる疾患だ。日本の大腸がん患者総数は約23万人だが、このうち1~5%がリンチ症候群だという。その多くは40代前後に発症し、多発することもある。
恐ろしい疾患だが、がんが大きくなる前のポリープ段階で、そのたびに内視鏡で取り除けば重大事は避けられる。埼玉県立がんセンターでは、リンチ症候群が判明した人には年1回の大腸内視鏡検診、女性にはさらに1~2年に1回の子宮体がん検診を勧めている。
これらの遺伝子診断の役割は、「遺伝性がん」体質を確認し、適切な予防を実施すること。一般的にみられるがんでは、残念ながらこうした予測はできないが、遺伝子とがん発症に関する解析がさらに進めば、より多くの遺伝性のリスクが明らかになるだろう。
■数時間、数万円で全ゲノム解析へ
これまでに解説してきた「個人のがん体質を決めている遺伝子の変化を調べる技術」は、実際の治療の際に、がん細胞の性質を調べることにも利用されている。…PR -
大塚家具で耳にする「プロキシーファイト」 過去のガチンコバトル一挙紹介!

大塚家具 <8186> の委任状争奪戦(プロキシーファイト)が激しさを増している。過去もプロキシーファイトとなる事例は何件かあったが、今回は何が異なるのか、過去の事例と比較して見ていく。
■サッポロHD vs スティール・パートナーズ
過去に起きたプロキシーファイトとして、2007年にビールメーカーのサッポロHD <2501> と、米系投資ファンドであるスティール・パートナーズの間で起こった例がある。
2006年からサッポロHD株の買い増しを進めていたスティール・パートナーズに対し、サッポロHDはスティール・パートナーズによる買収を防ぐために、2007年3月の株主総会を前に、新買収防衛策の導入提案を取締役会で決めた。
一方、スティール・パートナーズは、サッポロHD株の買収を進めたい狙いから、新買収防衛策に反対し、反対に賛同する委任状の送付を行った。結局、2007年3月の株主総会では会社提案の新買収防衛策は承認される一方、スティール・パートナーズの株主提案は否決され、サッポロHD側が勝利を収めている。
その後、2010年の株主総会の際にも、サッポロHDとスティール・パートナーズでは取締役選任に関して違った提案が出されたが、この時もサッポロHD側の提案が可決され、スティール・パートナーズの提案は否決されている。
サッポロHDとスティール・パートナーズの間に起こったプロキシーファイトは、会社の支配権をめぐって外部の投資ファンドが買収をかけ、それに反対する内部の現経営陣との間で起こった事例と言える。
■アデランスHD vs スティール・パートナーズ
サッポロHD相手のプロキシーファイトでは敗れたスティール・パートナーズであるが、2009年に起きたアデランスHD <8170> に対するプロキシーファイトでは勝利を収めている。
2009年5月末の株主総会時点でアデランスHDの26.7%の株式を保有していた米スティール・パートナーズは、株主提案として取締役の選任を提案。一方、米スティール・パートナーズの提案に反対するアデランスHDは、国内投資ファンドのユニゾン・キャピタルと組み、取締役の選任提案を提出した。
この取締役選任案に対するプロキシーファイトが行われ、結果、米スティール・パートナーズが提案した8人の取締役は8人全員が選任された一方、会社側提案のうち、ユニゾン・キャピタルが送り込んだ3名の取締役は全員否決された。… -
横浜のベテラン二階建てバス、引退へ 長寿の理由はその「生まれ」

横浜市交通局で唯一の二階建てバスが、2015年3月末をもって引退します。実はこの車両、通常なら法規制で12年しか使えない神奈川で、20年以上も活躍しました。なぜそれほど長く走ることができたのでしょうか。「生まれ」にその理由がありました。
12年しか使えない神奈川で21年走行
横浜市交通局から、2015年3月末をもって二階建てバスが姿を消すことになりました。1984(昭和59)年から横浜市交通局は二階建てバスを導入しており、今回姿を消すのは1994(平成6)年に導入された2代目の、「ヨンケーレ・モナコ」と呼ばれる車両です。
かつて横浜市交通局の二階建てバスは観光周遊バス「ブルーライン」として横浜市内の観光地を巡回していましたが、1980年代を中心に起こった「二階建てバスブーム」の収束や、経由地だったベイブリッジ人気の低迷から運行を終了。以降は定期観光バス「横濱ベイサイドライン」として活躍したものの、現在は二階建てではない車両に役目を譲り、1台が予備車両として残るのみになっていました。
さて、それにしても横浜市交通局が1984年に初めて導入した二階建てバスは約10年の活躍でしたが、2代目の「ヨンケーレ・モナコ」は1994年から21年もの活躍です。同じ事業者の車両ながら、なぜここまで2代目は在籍期間が長くなったのでしょうか。
特にディーゼル車が主役のバスは、「自動車NOx・PM法」という法律で使用期限などの規制が地域によって存在。神奈川県内では1994年が初年度登録だった場合、12年しか使用できません。にもかかわらず、です。
法規制を受けない理由はその「出生」に
横浜市交通局の「ヨンケーレ・モナコ」がそうした規制に影響されず21年も活躍できた理由は、「輸入車」だからです。この車両はベルギーのバス車体メーカーであるヨンケーレが、日産ディーゼル(現「UDトラックス」)のシャーシと組み合わせて製造した「モナコ」というモデル。それを日本に輸入した形です。
一般的に日本国内で生産された自動車は、「型式認定」という審査を国土交通省から受けて合格したのち市販されます。そしてこの際、排ガス規制についても認定が行われ、車検証へ合わせて記載されます。
しかし国内で製造されていない輸入車はこの「型式認定」を受ける必要がなく、「型式不明」として登録されます(車検証には便宜上の型式が記載され、この「ヨンケーレ・モナコ」は「RG620VBN」)。…
-
「リンガーハットの長崎ちゃんぽん」をカップ麺で うまみが凝縮したスープ

エースコックは、「タテロング リンガーハットの長崎ちゃんぽん」を2015年4月13日に発売する。
もちもちとした弾力のある太麺
長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」監修のもと、看板メニューである「長崎ちゃんぽん」をカップ麺で再現した。
なめらかでもちもちとした弾力のある太麺を採用。スープは、複数のポークエキスを使い、まろやかな豚骨の豊かな風味、野菜のうまみが凝縮されている。オニオンとごま油の調味料が付いてくるので、途中で味の変化も加えられ、飽きがこない。シャキシャキとした食感のキャベツにもやし、ぷりっとしたエビ、かまぼこ、人参など具材の彩りも豊か。
希望小売価格は税別205円。<J-CASTトレンド>
-
国際的ルールに追いつけない日本の「コピペ」教育
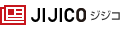
東大が初めてネット上で学生の不正を公開
 東京大学教養学部において、ある学生の期末レポートの75%がインターネットからのコピペだとして、「不正行為が認められた者は、その学期に履修した全科目の単位を無効とする」という厳正な措置が取られたと同校ホームページで発表されました。
東京大学教養学部において、ある学生の期末レポートの75%がインターネットからのコピペだとして、「不正行為が認められた者は、その学期に履修した全科目の単位を無効とする」という厳正な措置が取られたと同校ホームページで発表されました。
東大がネット上で学生の不正を公開したのは、今回が初めてです。昨年に発覚したSTAP細胞論文不正問題以降、大学でコンプライアンスに対する姿勢が厳しくなっていることを示すものとしてマスコミでも話題になりました。
しかしながら、ネットで簡単に情報を入手できる現代において、当の学生には他人の著作物を盗用したという罪の意識がどれだけあったのか疑問です。ただ単に盗用を数ある不正の一つとして文書で通達するだけでは不十分で、引用の出典を明らかにすることがグローバル・スタンダードであることを、入学当初にしっかり指導していたのでしょうか。グローバル化とは、英語での授業や留学生・外国人教員の数を増やすといった表面的なことではなく、このような国際的なルールを教えることでもあります。
盗用について明確なガイドラインが公開されていない
私がアメリカへ留学した30年前には、レポートの書き方についてガイダンスを受けた記憶があります。レポートに引用する際には、著作名はもとより、著者、公開年月、掲載ページなど、細かく出典を明記することに新鮮な驚きがありました。現在では、ハーバード大学、イェール大学、オックスフォード大学など、欧米の主要大学はいずれも「Plagiarism Policy」をHPで公表しています。
一方、日本では東大や京大、一橋、慶応や早稲田など主要大学のHPを調べてみても、盗用について明確なガイドラインを公開しているのは早稲田大学(教育学部)だけのようです。
20年前に提出した開発金融学のdissertation(修士論文)では、発展途上国における政府系金融機関と民間マイクロファイナンスの果たす役割を比較・考察し、ケーススタディとして中国工商銀行とバングラデシュのグラミーン銀行を取り上げました。まだインターネットが本格的に普及する前で、連日、図書館に通って書籍や論文、新聞、専門誌など、あらゆる資料を直接読み込むしか方法が無かったため出典は確実に判りました。インターネットが高度に発達した現代では、かえって元々の情報源をトレースすることは難しいのかもしれません。…
