産業・経済
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
キャリアアップへの障壁「ガラスの天井指標」とは?
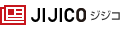
「ガラスの天井指標」で日本が世界ワースト2位に
 イギリスの経済紙エコノミストが発表した「ガラスの天井指標」によれば、1位がフィンランド、2位はノルウェー、3位はスウェーデンと北欧の国が上位を占めました。いずれも高等教育を受けた割合や労働参加率が高いことが特徴ですが、日本は韓国に次いでワースト2の27位となりました。
イギリスの経済紙エコノミストが発表した「ガラスの天井指標」によれば、1位がフィンランド、2位はノルウェー、3位はスウェーデンと北欧の国が上位を占めました。いずれも高等教育を受けた割合や労働参加率が高いことが特徴ですが、日本は韓国に次いでワースト2の27位となりました。
「ガラスの天井」とは、性別や人種などを理由に組織内で昇進できず低い地位のままである、「キャリアアップへの見えない天井」のことを指します。「glass ceiling」という単語の訳からそう呼ばれ、女性の社会進出が本格的に始まった1980年代から使われるようになった言葉です。
ガラスの天井指標は、OECD加盟国の中で算出可能な28か国を対象とし、「高等教育を受けた男女の数字」「女性労働参加率」「男女の賃金差」「女性の高位職進出比率」などの指標を元に算出されています。
能力や経験のある女性が昇進できる仕組みづくりが急務
日本と世界との違いが目立つのは、「女性労働参加率」「女性の高位職進出比率」です。日本では出産・育児時期に仕事を辞める女性が多いため、労働率が30代で低くなり、M字カーブを描くことがよく知られています。2013年の25歳~54歳の女性の就業率は69.2%ですが、先ほど挙げた北欧の国は80%以上をキープしています。
また、管理職の割合が低いことも特徴で、アメリカが43%、フランス39%に対して、日本では11%にとどまっています。出産・育児を経ても働き続けられる環境の整備と、能力や経験のある女性が昇進できる仕組みづくりが急務であることが分かります。
小さな一歩の積み重ねが、「ガラスの天井」を打ち砕く大きな一歩
「詐欺師症候群」という言葉をご存知でしょうか。自己評価が低く、仕事で高い評価を受けても「周りの人のおかげ」「実力ではない」「いつか自分には力がないことがバレてしまうのでは」と不安を思ってしまうことで、欧米の女優や大企業の役員女性が発言して話題になった言葉です。
女性のキャリアアップが進まない裏には、環境の整備が整ってないことだけでなく、女性側にもこのような無意識な考え方があることも予想できます。小さいころから「女の子なのだから」と控えめに振る舞うことを良しとされた環境で育ったことや、仕事で目立つ業績を出すと「女性なのに」と周囲が特別扱いする環境だったこと、それらが複雑に絡み合い、素直に自分の評価を受け入れることができず、低い地位のままでいる女性をつくり続けている可能性もあるのです。…
PR -
中国、アジア開銀を批判 「官僚主義で煩雑」

【北京共同】中国の楼継偉財政相は22日、アジア開発銀行(ADB)の運営が「官僚主義で煩雑で、最良とは言えない」と批判した。中国が主導して設立するアジアインフラ投資銀行(AIIB)は、既存の国際金融機関とは異なる運営方針を取る考えを示した。
北京で開かれた経済フォーラムでの発言を、中国メディアがインターネット中継で伝えた。
フォーラムに同席したADBの中尾武彦総裁が、AIIBの投資対象のプロジェクトが環境保護への配慮などが必要だと指摘したところ、楼氏は「(欧米や日本が中心の国際機関の)既存の制度が全て良いとは思わない」と反論した。
-
保存用ポリ袋でガーリックペーストを作れば、後片付けもラクラク


ガーリックペーストは、ピリッとするニンニクの味やまろやかな舌触りを加えたい時など、どんな料理にも使えます。厨房の料理人も、ご家庭での調理でも、通常は包丁の刃を使ってまな板の上でニンニクを集めながら作る方法でペースト化しますが、料理レシピを紹介するサイト「Food & Wine」では簡単にできる画期的な作り方を紹介しています。
Justin Chappleが、こちらの動画でその方法を披露しています。これなら作る量の調節ができますし、何よりも、ニンニク臭さの後片付けをしなくてすみます。皮をむいたニンニクと塩をジッパー付きの冷凍用バッグに入れた後でジッパーを閉め、ミートマレットで軽くたたいて砕きます。次に麺棒を使い、細かく砕いたニンニクをペースト状になるようにつぶします。ご覧ください! 煮込み料理、ディップ、サラダドレッシングなど、さまざまな料理に使えるガーリックペーストの完成です。
もし頻繁に使うのであれば、たくさん作り、小分けにして冷凍すれば使う時も簡単です。とはいえ、毎回新鮮なペーストを作るのも良いでしょう。いずれにしろ、瓶詰のガーリックペーストにお金をかける必要はもうありません。
Susannah Chen(原文/訳:コニャック)Photo by Shutterstock.
元の記事を読む
-
勝負は退社前の5分!デキる働き女子が「帰る直前にやるべきこと」3つ


定時も過ぎたし、そろそろ帰ろう!と思った時、仕事が終わったらすぐにパソコンの電源を落としてそそくさと帰ってはいないだろうか? そして、次の日仕事に追われてまた残業……というような悪いループにはまってはいないだろうか?
実は、ササッと帰るその前に、デキる社員が必ずやっていることがあるのだ。
今回は、企業で研修などの人事を担当していた筆者が、そのような“評価の高い社員が退社前にしていること”について、経験を元にご紹介していこう。
■1:今日やったことをまとめて“見える化”する
若手社員なら、毎日“日報”などの提出を求められているかもしれないが、社歴が長くなるとそのようなことは求められなくなる。しかし、今日やらなくてはいけないことをどのくらいやれたのか、またどのくらい成果があったのかを確認することは、非常に重要なこと。
自分で目に見える形でまとめることで、何が今うまく進んでいないのか、時間がかかっているのかを把握することができ、次の日に活かすことができる。
一度、1日に行った業務について、かかった時間などをすべて残してみるといいだろう。思わぬことに時間をとられていることが分かるかもしれない。
■2:明日やるべきことの優先順位を決めておく
今日の振り返りができたら、それを元に明日やるべきことをまとめ、優先順位をつけておこう。朝出社してから決めるより、今日の結果を覚えているうちに計画することで、確実に仕事をこなすスピードが上がる。
■3:明日のスケジュールを確認する
やるべきことを決めていても、明日は会議がいっぱいでした……。ということになっては計画が狂ってしまう。また、当日に思わぬ来客など別の予定が入り込むことも多い。
明日のスケジュールを確認し、自分の仕事に集中できる時間をしっかりと把握しよう。どうしても明日中に集中して終わらせたい事がある場合、スケジュールに「○時~○時:作業時間」などと入れ込んでしまい、他の人が予定を入れることができないようにするのも手だ。
周りに振り回されて自分の仕事が進められないようなことがないよう、前日に時間配分も計画しておくことがおすすめだ。
以上、“評価の高い社員が退社前にしていること”についてご紹介したが、いかがだろうか?
ご紹介したことは、当たり前のことではあるが、実際にできている人はどのくらいいるだろうか? このような積み重ねが、日々の仕事の早さや正確さにつながり、周りから信頼され、評価されることにつながるのだ。
帰宅前の5分でいいので、ぜひ時間を作って実行してみてほしい。
-
EV・PHVの補助金強化!次世代エコカーの普及が加速するか


次世代エコカーとしてあげられる電気自動車(EV)やプラグインハイブリット車(PHV)は、大量生産が可能になれば量産効果によって価格は下げられる。しかし、その手前がむずかしい。
これから普及すべきもの、普及してほしいものであっても、大量生産に至らない段階の場合は価格が下げられない。そこで、その製品が国の政策に合致するものであれば、国が補助金を出して、普及しやすい状況を作るわけだ。
■ 次世代エコカーの普及を促進する
経済産業省から電気自動車の普及促進にかかわる取組を強化する旨の発表がなされた。ここでいう電気自動車とは、完全に外部電源から充電した電池のみで走るEVと、外部電源から充電した電池で走れるが電池切れの際はガソリンエンジンで走行することもできるPHVを指す。
EVや電池のみで走行している状態のPHVは、走行中には二酸化炭素を排出しない。火力発電所で発電した電気を消費する場合は、発電の段階で二酸化炭素を排出していることになるが、それでもガソリン車より効率がいいので、二酸化炭素の排出量は減らせる。そういった点でエコだといわれる(ただし製造過程や廃棄過程での環境負荷を考慮していない議論が多いので注意が必要だ)。
そこで、経済産業省は
環境・エネルギー制約などグローバルな課題を見据えた先進的国内市場を世界に先駆けて形成するとともに、自動車産業のグローバル展開を進める(『自動車産業戦略2014』より)。
などの目的のために、次世代エコカーとして期待されるEVやPHVへの補助金を強化しようというのだ。
■ 購入とインフラ整備の促進
その内容は、
(1)EV、PHVの購入費用の補助。
(2)インフラ整備のための充電器の購入費用及び設置工事費用の一部を補助。
(3)一料金区間の料金額が1,000 円(普通車の場合)を超える走行に対して、利用状況に応じた調査協力費の支給。
といったものだ。(1)はもちろん購入の促進、(2)は様々な場所への充電器の設置の促進、そして(3)は電気自動車の高速道路利用を短期的に促すことで、高速道路上の具体的な充電器ニーズを調査するという目的がある。
PHVの場合は問題ないが、EVの場合は航続距離が問題となる。ガソリンの給油に比べて、充電には時間がかかるからだ。しかし、急速充電器が設置されていれば、通常の家庭用100ボルト電源よりはずっと短い時間で充電できる。

実際のところ、1日の走行距離が数十キロのケースがほとんど、という使い方のユーザーは多いはずだ。…
